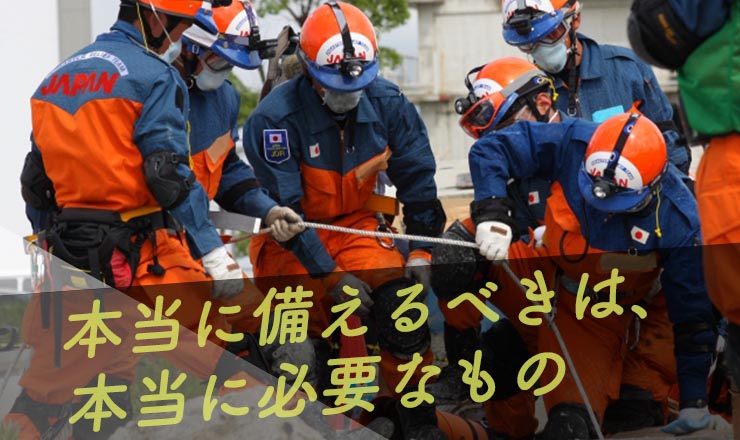
皆様の会社ではどのような地震(災害)対策を実施していますか?
防災備蓄をしている企業の多くは各都道府県の条例(東京都の場合:東京都帰宅困難者対策条例)の基準量を確保しており、最低限必要な量としては問題ありません。
しかし、防災備蓄品はそもそもどのような目的で確保しているのかの視点から考えると不足している備蓄品や選定方法があります。
本記事では防災備蓄品収納1級プランナー / 職場備蓄管理者(一般社団法人 防災備蓄収納プランナー協会)の目線でオフィスに本当に必要な備蓄品についてお伝えします。
お客様とお話をしていると、「お水や食料などの防災備蓄品の確保」を1番に取り組みとしてお伺いします。しかし、それだけでは十分ではありません。なぜなら、防災備蓄品を使うシーンは入居ビルであり、まずは自分の身の安全が確保されていることが大前提だからです。そのため、対策としては下記優先順位で対応をします。
災害対策の優先順位
①入居ビルの耐震性の確保
②キャビネットや複合機の転倒、落下防止
③初期消火への備え
④埋もれた、閉じ込められた人を救出する備え
⑤被災後の生活の備えとして防災備蓄
このように、災害を乗り越え、身の安全を確保した上でライフラインや物流が停止しても生活できる備えが“防災備蓄品”の役割です。
「ライフラインや物流が停止しても生活できる備え」を念頭に置き、次はどのような備蓄品をそろえればいいのか考えていきましょう。
ウチダシステムズとして推奨しているオフィス備蓄品の一部は以下の通りです。
3日分を目安に準備
水:1日3ℓ×必要人数分*
主食:1日3食×必要人数分*
副食:1日3食×必要人数分*
簡易トイレ:1日8回(一般平均)×必要人数分*
安全:ヘルメット、軍手
情報:ラジオ、蓄電池
生活:ランタン、寝床、冷暖器具、食事道具、救急薬品類
※必要人数は在宅勤務状況を考慮した平均出社人数や、帰宅可能者を考慮して算出

ポイントは、推奨備蓄品の中で特徴的なのは各都道府県の条例の多くで「食料」と示されている項目をきちんと「主食」「副食」と分けている点です。
皆様のオフィスで備蓄食として確保しているのは乾パンやお米など炭水化物ではありませんか?実際に3日間オフィスで過ごすと考えると、同じような食事メニューでは精神的に、また食物繊維不足など体調的にも身体に負担がかかることが想定されます。(“災害太り”なんて言葉もありますよ…!)
そのため、きちんと「副食」を保管することは災害中の体調管理で重要な役割を担います。
バランスの良い食事、リフレッシュのためのお菓子の確保も心がけましょう。

続いて、推奨備蓄品の中で配慮が必要なのは「保温シート(主にアルミシート)」です。
こちらも食料と同様に実際に使用するシーンを考えてみましょう。就寝時、寝返りをうつとレジャーシートのようなガサガサとした音が鳴るため、自分だけでなく周囲の方の就寝を妨げる恐れがあります。そのため、毛布や音の鳴りにくい製品の選定が精神的なストレスを少しでも減らす工夫に繋がります。

また、推奨備蓄品で注意したいのは、オフィス内の備えとして必要なものを挙げているため個人の生活用品が含まれていないということです。そのため、各従業員は個人の判断で下記を準備するよう社内に声がけをしましょう。
個人で用意したい備蓄品の一例
・家族や友人への連絡先
・地図(自宅周辺を含む)
・スニーカー
・歯ブラシ
・着替え
・下着
・お菓子
・コンタクトレンズの管理用品や眼鏡
・生理用品

(参考)私の防災ポーチの中身の一部です
このように防災備蓄品を選定するポイントは、実際に使用するシーン、3日間生活する事を想定することです。少しの工夫が数日間生活する際のストレス軽減に繋がります。
最後に、防災備蓄品は「1. 防災備蓄品の役割とは?」でお伝えした通り、“災害を乗り越え、身の安全を確保した上で、ライフラインや物流が停止しても生活できる備え“です。
その上で「2. 何をそろえればいいの?」でお伝えした通り、実際に使用するシーン、数日間生活する事を想定して選定しましょう。
企業の災害対策は危機管理の基本です。しっかりと整え、社員を守っていきましょう。
防災備蓄品をご検討の際は本記事のような視点でご提案させていただきます。
ぜひウチダシステムズにご相談ください。
2018年ウチダシステムズ入社。
オフィス・組織を創り上げるコンサルタントとしてプロジェクトをお手伝いするVECTORチームに所属。
防災備蓄品収納1級プランナー、職場備蓄管理者(一般社団法人 防災備蓄収納プランナー協会)を取得し、社員を守る災害対策もサポートする。

ライター佐藤 沙樹
ウチダシステムズについて
詳しく知りたい方はこちら